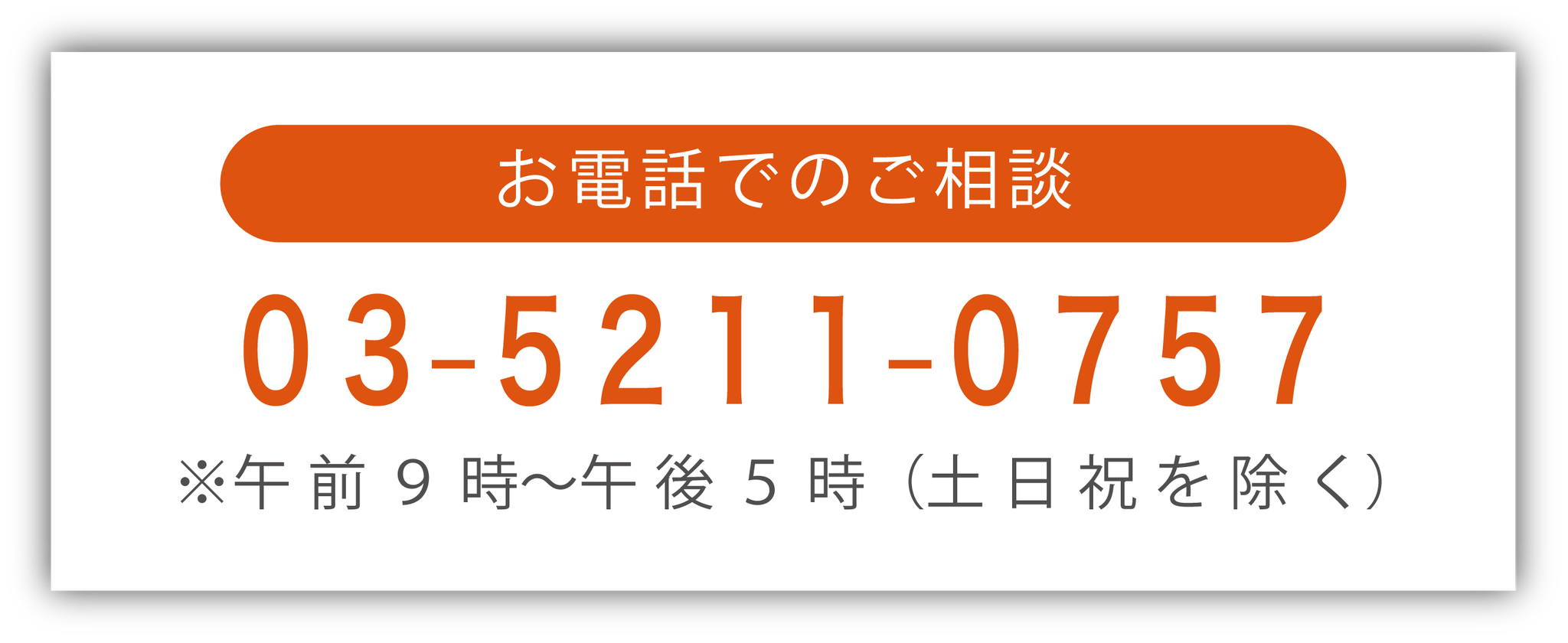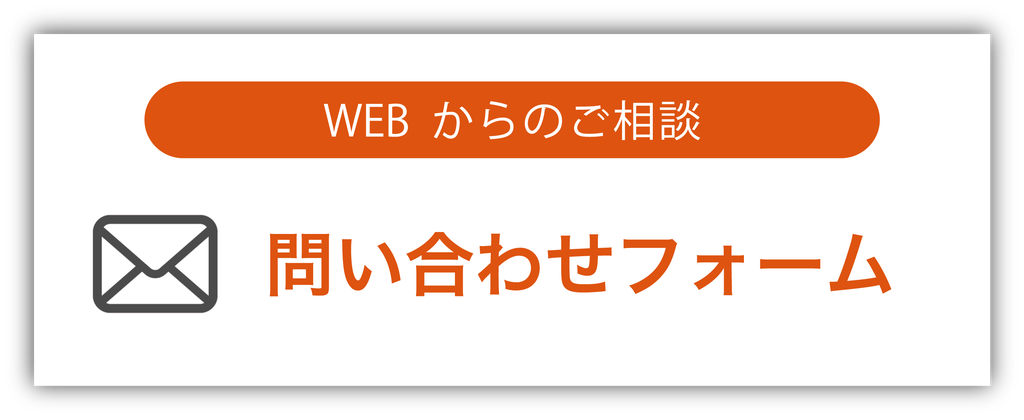マイホーム借上げ制度 ご利用ガイド
申し込み条件
事前の備えで、マイホームを「負債」にしない
「マイホーム借上げ制度」を利用するには、JTIの定める耐震強度を備えた、日本国内にある住宅をお持ちである必要があります。
日本に居住する50歳以上の方(原則として国籍は問いません)、または海外に居住する50歳以上の日本人。及び両者の共同生活者(1名まで)。50歳以下の場合の利用条件は、下記「利用者が50歳未満の場合」をご覧ください。
共同生活者とは? オーナーさまの配偶者、内縁関係の者、その他契約時に特定同居人として指定した者1名のこと
オーナーさまが単独所有、または第三者と共同所有する、日本国内にある住宅をお持ちであること
一戸建て、共同建て(タウンハウスなど)、マンションなども対象となり、現在住んでいる必要はありません。
JTIが指定する業者の建物診断をオーナーさまの負担で受け、必要な場合には耐震工事を制度利用者の負担で実施すること
築後25年が経過した物件については建物診断が必要となります。築25年以内の物件については、簡易の外観調査を行います(無料)。
土地について所有権または適法な権利(借地権、長期の定期借地権など)を持っていること
現在オーナーさま以外の者が住んでいる場合には、原則として制度利用を申し込む時点で明け渡しが完了していること
建物が事業用物件でないこと
住宅の一部が店舗や事務所である場合にはその部分は原則として借り上げられません。また賃貸アパートや当初から賃貸併用(自己居住部分と賃貸部分が一体となった建物)である住宅の賃貸部分は、原則として借り上げの対象とはなりません。
建物が建築基準法や建築基準関係規定に違反していないこと
共同所有の場合は、登記簿に記載された共有者全員が制度利用を承諾し、契約の際当事者となること
JTIから要請があった場合は速やかに登記を行うこと
賃借権の登記は原則行う必要はありませんが、JTIから要請があった場合は速やかに登記を行っていただきます。登記費用はオーナーさまの負担となります。
抵当権が設定されている住宅の場合、JTIで借上げの可否について審査を行うこと
詳細は、JTIまでご相談ください。
破産や民事再生の申し立て、強制執行を受けていないこと
対象住宅に関する固定資産税の滞納や、その他不動産関連の支払いが滞っていないこと
オーナーさまの負担で住宅に火災保険をかけること
利用者が50歳未満の場合 利用者が50歳未満の場合は、以下の条件のうちいずれかを満たす必要があります。 条件は柔軟に判断しますのでご相談ください。 「かせるストック」の認定を受けている住宅であること 「かせるストック」についてはこちらをご覧ください。 相続や生前贈与により取得した家をお持ちの方 家を相続や生前贈与により取得した後、当面お住まいになる予定のない方が対象です。制度利用申し込み時点で、すでに空き家であることが条件となります。 すでに名義が子供になっている場合に適用されます。 転勤・転職、海外赴任で住みかえをなさる方 以下のような事情で住みかえが必要な方 ○家族の介護・支援、病気療養 ○家族状況の変化(結婚、子供が増えた、家族が亡くなった、離婚等) ○その他住み替えを余儀なくされる事情 定期借地上の家 その他、アパートのように事業目的でない住宅で、現状人の住んでいない物件をお持ちの方 急な減収で住宅ローンの返済が厳しくなっている方(金融機関への相談が必要です) 一時的にご両親の家などに転居していただいた上でJTIが家を借上げ、賃料収入をローン返済にあてます。経済状態が改善されて自主返済が可能になった時は、3年ごとの契約を更新しなければ、再びマイホームに住むことができます。 起業支援金・移住支援金を受け取られる予定の方 内閣府による地方創生事業の一環である、移住支援金・起業支援金を受け取られる方に適用されます。支援金についてはこちらのページをご覧ください(外部リンク)。
最低家賃保証型をご利用の場合 最低家賃保証型とは?
以上の条件に合わせて、以下の条件を満たす必要があります。 ・戸建てであること(マンションは個別判断となります) ・5年ごとの建物診断(費用はオーナー負担)を行い、必要な場合は 修繕を行うこと ・耐震診断を行うこと ・以下のいずれかに当てはまること 1. 2000年(平成12年)5月31日以前に建築確認を受けて建てられた物件 の場合、建物診断(耐震・劣化)を受診し、耐震診断結果が基準値等級1に 満たない結果であった場合は耐震等級または上部構造評点(iw)を1以上に 引き上げる耐震改修工事を実施すること 2. 2000年(平成12年)6月1日以降に建築確認を受けて建てられた物件の 場合は、劣化診断を受診すること(耐震診断は不要) ・耐震改修工事を実施する場合は、5年のリフォームかし保険に加入すること
おまかせ借上げをご利用の場合 おまかせ借上げとは?
以上の条件に合わせて、以下の条件を満たす必要があります。 ・戸建てであること(マンションは対象外) ・改修後に入居者を見込める地域であること ・JTIが耐震診断を実施すること ・耐震診断の結果、以下の工事をJTIまたは入居者が行う場合があることに合意すること 1. 耐震性が現行基準に満たない場合、耐震補強工事 2. 入居者負担での内装・設備のリフォーム工事 ・10年以上の定期借家契約を結ぶこと(中途解約不可)
申し込みまでの流れ
情報登録を行う
カウンセリングカードをご記入いただき、郵送・FAXいずれかの方法でJTIまでお送りください。
ハウジングライフプランナーのカウンセリングを受ける
JTIが認めた有資格者より、マイホーム借上げ制度についての詳しい説明を行います。その際、住みかえ先の情報や住まい、生活資金のプランニング、公的支援についてのアドバイス、現在の家の修繕・リフォームについてなど、移住・住みかえ全般に対するご相談やお悩みもありましたら、あわせてご相談ください。
賃料査定を行う
JTI協賛事業者が、実際に建物を見たうえで賃料査定を行います。
(※この段階でお出しした賃料は、実際の賃料と異なる場合もあります。)
制度利用申込書を提出する
申込手数料(18,700円/税込)を頂戴します。このとき同時に、ハウジングライフプランナー資格保有者から、借上げのための建物賃貸借契約の内容について説明を行います。
建物診断の実施
JTIの借上げ基準に適合している住宅かどうかを判断するための調査です。費用は制度利用者さまのご負担となります。調査は「耐震診断」と「劣化診断(建物の劣化や雨漏りなどの検査)」を行います。
(※昭和56年6月1日(新耐震基準)以降の建物で大きな増改築などがない場合は、耐震診断は不要です)
補強・改修工事の実施
建物診断の結果、必要な場合は工事を行います。費用は制度利用者さまのご負担となります。
JTI協賛会社による入居者募集
JTIより、借り上げ条件を記載した承認通知書を受領し、契約成立
賃料の支払い
制度利用者さまの退去・ハウスクリーニングの後、入居者が入居された日から借上賃料をお支払いします。
中途解約について
対象住宅に戻らねばならない事情が生じた場合や、お子さま等に住まわせることにされた場合、対象住宅を売却することを決められた場合等には、中途解約をすることが認められています。
ただし、入居者の居住権を保護するために、次の制約があります。
解約通知書の提出
解約が必要となった事由を記載してJTIまで提出していただきます。
※解約通知書は、制度のご利用時にお渡ししています。
申し込み時点で入居者がいる場合
JTIが解約通知を受領した時点において、対象住宅に入居者が住まれている場合には、その入居者との転貸借契約が終了したときに同時に契約が終了します。
申し込み時点で入居者がいない場合
JTIが解約通知を受領した時点において、対象住宅に入居者がいない場合には、通知書を受領した時点で解約となります
解約のできないケースについて
JTIが同解約通知を受領したときから転貸借契約の期間満了までの期間が、法律で定められた入居者への告知期間である6ヶ月に満たない場合には、JTIが入居者に告知を行ってから6ヶ月が経過するまでお待ちいただきます。
解約の拒否について
JTIが解約権の濫用であると判断する場合には、借地借家法の規定に基づいて正当事由がない限り解約に応じないことがあります。
緊急の場合の解約について
利用者の健康状態、経済状態その他の事情から、制度利用者が対象住宅に戻らないといけない切迫した事情がある場合には、入居者との転貸借契約を合意解約できるように極力努力します。
ただし、交渉の結果どうしても解約することができない場合には、通常の手続きによる解約しかできません。JTIの努力義務は法的な義務ではありませんので、その成果についてJTIは一切責任を負いません。
契約が終了となる場合
以下の場合は、機構が契約終了の通知を制度利用者(オーナー)さまに行い、その後契約の更新は行いません。ただし、家賃に担保権を付与した提携ローンの残高が残っている場合は、当該提携ローンが完済されるまでの間継続します。
- 制度利用者(オーナー+同居人)の両方の死亡
- 土地に対する権原が所有権以外の場合に借地権等が何らかの理由で期限前に解約された場合
- 対象住宅が減耗毀損し、機構が応急措置を講じた上で、制度利用者(オーナー)に改修を要求したが、制度利用者(オーナー)がこれに応じないとき
- 経年劣化により、対象住宅を継続して転貸するには、経常的な修繕費を超える資本的支出が必要であると機構が判断し、その旨を制度利用者に通知したにもかかわらず、制度利用者(オーナー)が当該修繕を行わない場合
- 不動産関連諸費支払いの悪質な懈怠があり、制度利用者(オーナー)の賃料収入から継続して支払うことが困難な場合
- 制度利用者(オーナー)による機構の円滑な業務遂行の妨害があり、制度利用者(オーナー)に中止を要求したが、制度利用者(オーナー)がこれに応じないとき
- 制度利用者(オーナー)から中途帰還に基づく契約解約の申し入れがあった場合
- 制度利用者(オーナー)側の都合により契約の継続が困難であると機構が認めるとき
- 制度利用者(オーナー)が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団、暴力団員、そしてこれらと密接な関係を有する者であると判明したとき
- その他、転貸が困難であると機構が判断するとき
また、以下の場合は、即時に契約を終了します。
- 対象住宅の焼失・毀損
- 機構の責に依らない事由で対象住宅を賃借、もしくは、転貸することができなくなった場合
- 機構が解散し、その権利義務を引き継ぐ機関が解散の時点で存在しない場合
- 転借契約の即時解約事由に該当する事由が発生し、制度利用者(オーナー)が即時解約を書面で請求してきたとき
入居者について
どんな人が入居者になるか
主として子育て世代に転貸します。なお、住宅の状態や地域の状況などの理由で一定の賃貸収入を確保するために必要な場合には、オーナーさまに確認の上で事務所・店舗等の目的で転貸する場合があります。
契約について
契約期間
3年以上の定期借家契約です。制度利用前に、貸し出しの期間をオーナーさまが決定します。
借上げ賃料および空室時保証家賃の決め方
対象住宅のある地域における賃貸市場の動向や建物の状況等から判断して、JTI協賛会社あるいはハウジングライフ(住生活)プランナーが査定し、JTIが承認することで決定します。
空室時保証賃料は原則として毎年見直すものとし、変更があった場合のみ書面でオーナーさまに通知します。
賃料お支払いの開始時期
マイホーム借上げ制度の利用開始時期は、最初の入居者が入居した時点からになりますので、借上げ賃料が支払われるのは、その時点からになります。制度利用の申し込みと同時に賃料が保証されるわけではありません。
お支払いいただく費用について
住宅や設備の管理費
入居者は退去の際、経年変化および通常の使用による住宅の損耗等の復旧については、その費用を負担しません。ただし入居者の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、入居者の責任による住宅の損耗等があれば、その復旧費用は入居者が負担することになります。
制度開始にあたってお支払いいただく費用
JTIが求める耐震補強等の修繕と、賃貸物件としての必要最低限の修繕が必要です。
制度開始後にお支払いいただく費用
オーナーさまが設備として残していったもの(エアコン、トイレ、ガスコンロなど)に故障が発生した場合は、オーナーさまの負担で修繕が必要となります。
なお、退去時の室内クリーニングおよびエアコンクリーニング費用は、入居者が負担します。
初期費用に不安がある方は・・・
初期費用や、制度利用開始後の賃料について不安のある方のための制度をご用意しております。
最低家賃保証型 最長35年間、最低保証賃料をお約束します。保証期間中は、仮に賃貸市場が大きく下がったり、入居者がいない期間であっても、お約束した以上の家賃をお支払いします。 おまかせ借上げ制度 借上げにあたって、通常オーナー様が事前に行う耐震改修費用、内装・設備のリフォーム工事を、JTIが代行します。工事の費用は家賃の一部から回収。 初期費用負担が少なくすむため、「住まない家にお金をかけたくない」という方にぴったりのタイプです。