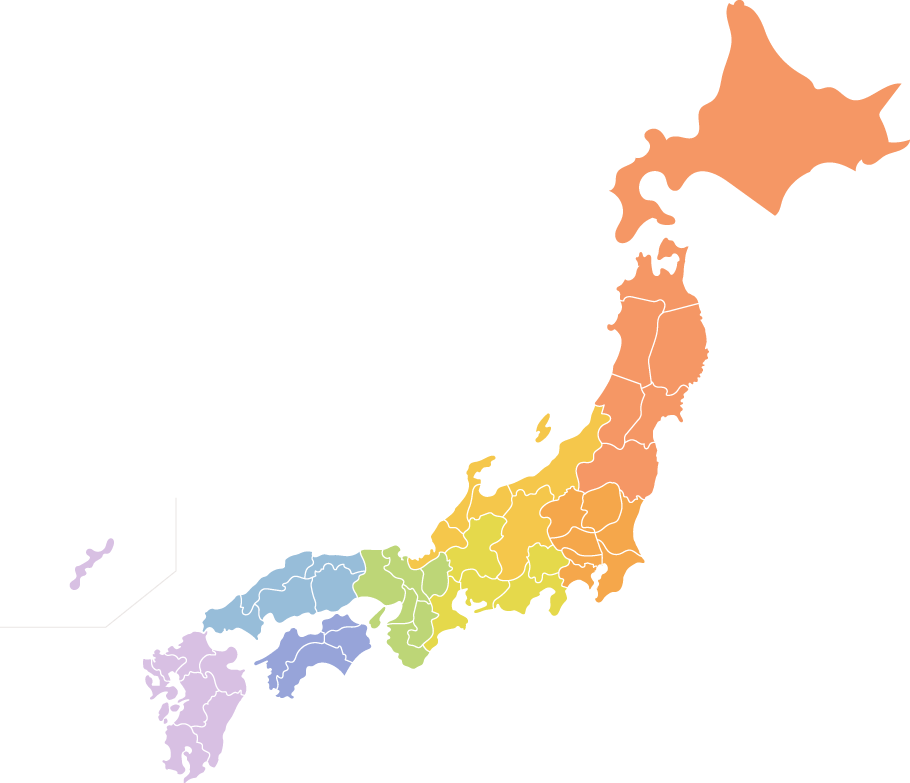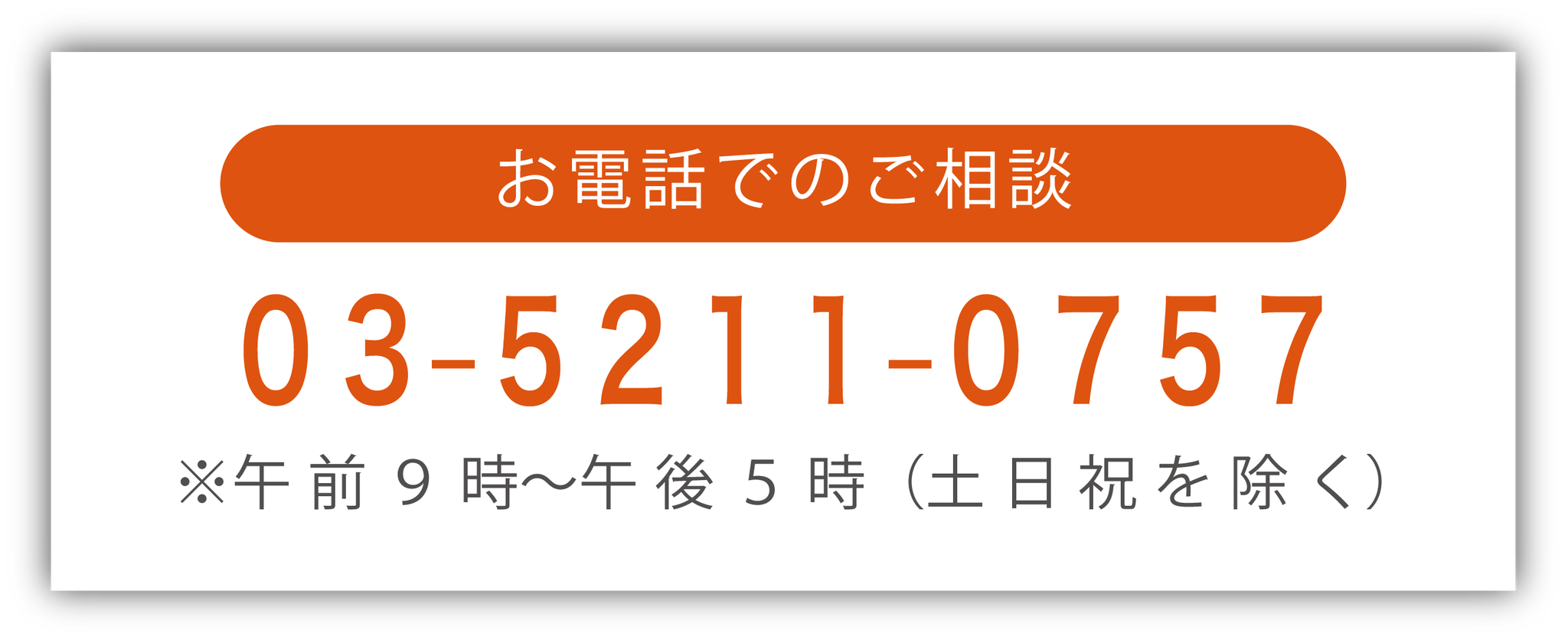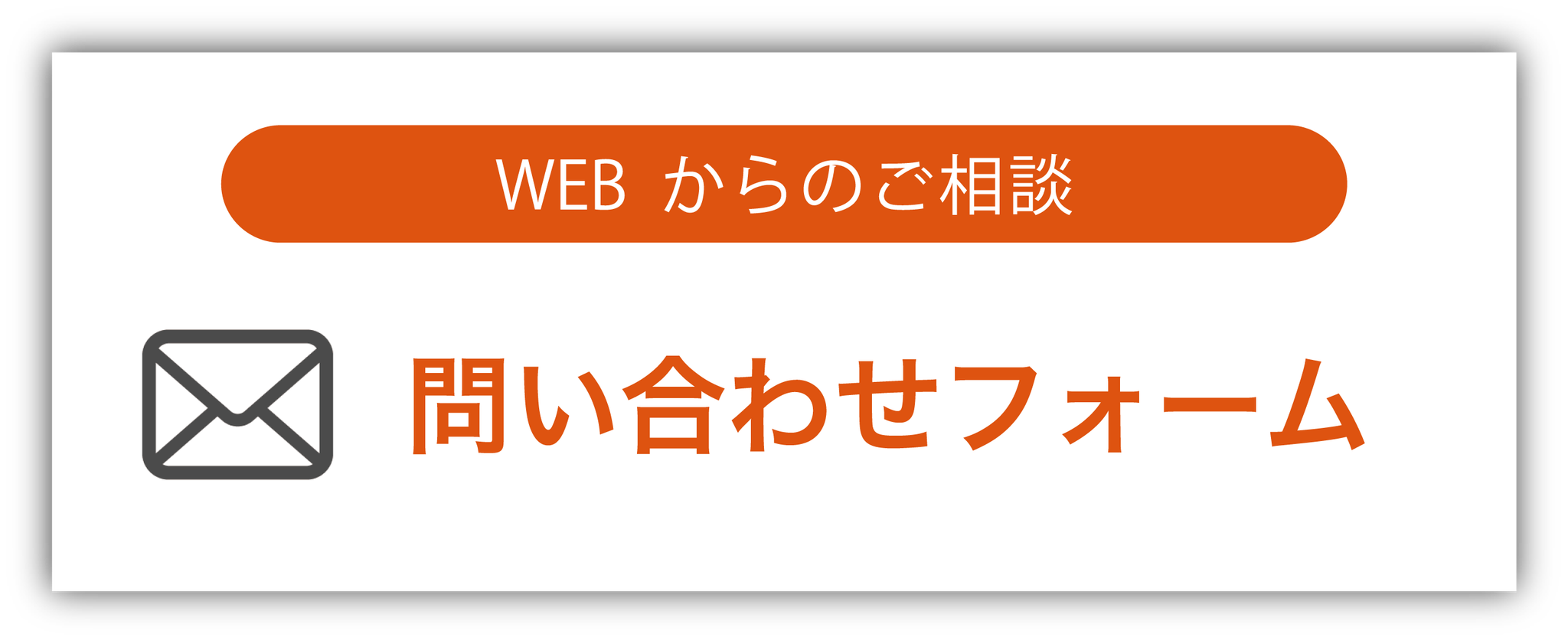JTIについて
住まいをゆたかに。明日をもっとゆたかに。
マイホーム借上げ制度を中心とした様々なサービスや技術によって、日本の住宅に、金融資産としての価値をもたらします。また、かせるストックなどの証明書の発行により、長期優良住宅を建築する意義を確立。社会に良質な住宅ストックを循環させます。マイホームを、日本が誇れる金融資産に。これまでにない金融技術と制度で、JTIが日本のハウジングライフを支えてゆきます。
代表理事
大垣 尚司
青山学院大学 特任教授

Profile
東京大学卒業後、日本興業銀行、アクサ生命保険専務執行役員、日本住宅ローン社長、立命館大学大学院教授などを経て、現在、青山学院大学教授。金融技術研究所 所長。
2006年に「有限責任中間法人移住・住みかえ支援機構」(現、一般社団法人 移住・住みかえ支援機構)の代表理事に就任。著書に『ストラクチャードファイナンス入門』『金融と法』『49歳からのお金ー住宅・保険をキャッシュに換える』『建築女子が聞く 住まいの金融と税制』、2023年発売「家の買い方、持ち方が変わる!残価設定型住宅ローン」など。
MESSAGE
人生100年時代を迎え、一つの家を終の住処とする時代から、ライフステージの変化に応じて住む場所や住む家を替えていく時代になりました。
家は庶民にとって老後に備えた最大の資産。買った家や相続した家に住まなくなって売らずに持っておく人は少なくありません。 しかし、人の住まない家はすぐに傷みます。
JTIはそんな多くのみなさんのために、国の基金による支援や、大手企業等の協賛を得て、日本全国を対象に、住まなくなった家を借り上げて、若い世代を中心に転貸することで、家を売ることなく安定的な収入に変えることができる、マイホーム借上げ制度を運用する非営利の機関として2006年にスタートしました。
おかげさまで、今では毎年10億円規模の家賃を利用者のみなさんにお支払いするまでに育ちました。2008年からは、優良な住宅について利用年齢を撤廃したり、将来借り上げたときの最低家賃の金額を保証する、かせるストック証明書制度を開始し、証明書を発行した住宅の棟数は12万戸を超えております。
今後も、良質なマイホームを世代間で住み継いでいくための社会インフラとしてサービスの向上、新しいサービスの構築に努めて参ります。
理事
伊藤 明子
株式会社まち・ひと・しごと研究所 代表取締役
Profile
1984年京都大学工学部建築学科卒業、同年建設省入省。住宅局住宅総合整備課長、住宅生産課長、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長兼内閣府地方創生推進室次長、国土交通省大臣官房審議官(住宅局担当)、国土交通省住宅局長を経て消費者庁長官に就任し、2022年退官。株式会社まち・ひと・しごと研究所 代表取締役。
MESSAGE
皆さんにとって、住宅って何でしょうか。
住宅は、もちろん、私たちの生活の大切な器です。同時に、その取得は、人生において最大といってもいい買い物でもあります。それにもかかわらず、私たちは、取得、要は入口には熱心なのに、住まなくなったらとか、手放すことになったら、といった出口には、十分な関心を寄せてきませんでした。
人生100年時代、ライフステージにおいて様々なイベントがあります。単線型ではなく、複線型の人生設計がなされる中、住まいも、様々な選択ができるようにしておく必要があります。
移住・住みかえ支援機構は、個々人の人生プランに対応し、大切な個人資産である住宅を、安心して資金化できる選択肢を用意しています。
そして、その住まいは、社会にとっても重要な資産として、住み継がれていきます。いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う。空き家問題などは、個人、地域、社会全体の課題です。社会全体で、バトンを受け継ぐ。住宅の出口戦略を考えて、実現することは、個人の生活のためとあわせて、持続発展可能な社会の課題解決のためにも、価値のあることです。
個人にとって、社会にとって、いい選択を考えてみませんか。移住・住みかえ支援機構は、そのお手伝いをします。
さて、あなたにとって、住宅とは、住まいとは、何ですか。
理事
合田 純一
一般財団法人 住宅保証支援機構 理事長
Profile
1978年、東京大学工学部都市工学科卒業後、建設省(現国土交通省)に入省。 住宅局住宅総合整備課長、同省国土技術政策総合研究所副所長を歴任。 独立行政法人住宅金融支援機構理事、一般社団法人プレハブ建築協会専務理事株式会社日本建築住宅センター代表取締役社長などを経て、2023年より一般財団法人 住宅保証支援機構理事長。
MESSAGE
JTIが発足したのは2006年で、同じ年に国の住宅政策体系が大きく転換し、それまでの住宅建設計画法に基づく量的充足中心主義から脱却し、国民の住生活の向上のための幅広い政策を意図する住生活基本法が制定され、住生活基本計画がスタートしました。この住生活基本計画の下、住宅の品質・性能の維持・向上、ストック対策、住宅流通の円滑化など新しく幅の広い政策の展開がなされるようになりました。JTIは国の政策を先取りして、所有と居住の分離・流動化、真の住宅価値の活用などをベースとした新しい市場開拓を行っています。特に今日的に地域創生や国民の住生活の向上・負担軽減の観点から重要となっているのは、地域活性化でキーとなる空家の活用の一方策としてマイホーム借り上げ事業の活用や、長期優良住宅の持つ建物の長寿命性だけでなく、住宅価値が長期にわたり保持される特性を活用することにより、家賃保証制度や残価保証をベースとした新しい金融商品の開発などの住宅価値保証事業の普及です。是非とも、地方公共団体、住宅建設事業者、金融事業者、不動産事業者の方々がJTIの事業内容をご理解いただき、事業のさらなるご活用をいただければ幸いです。
監事
村本 孜
成城大学 名誉教授
Profile
一橋大学大学院博士課程修了。応用経済学の金融論を専攻。主に国際金融、リテール金融を専門領域とする。国土交通省独立行政法人評価委員会住宅金融支援機構分科会会長などを務める。著書に『信用金庫論』、『元気な中小企業を育てる』など。
MESSAGE
35年程前、国際居住年の行事で国際シンポジウムを催し、英・米・仏・独・韓国から実務家や研究者に来て頂き、住宅金融・税制を議論しました。金融自由化の中で住宅ローン債権の証券化や税制の優遇措置などがテーマでした。迫り来る高齢社会に如何に対応するかもポイントでした。
海外からの参加者からリバースモーゲジの提案があり、日本での導入の必要性を感じました。個人が高齢期に備えるには貯蓄ですが、平成期に賃金が横這いだったように、誰もが老後資金を十分に蓄えられるわけではありません。そこで生涯所得の3割余を費やして取得する住宅を老後資金として活用することが大切になります。
建設省や厚生省が研究会を持ち、専門家が議論しましたが、なかなか制度化には壁がありました。その突破口を開いたのが移住・住みかえ機構です。代表理事の大垣尚司氏のアイデアで、住替え型リバースモーゲジと呼ばれるものです。個人的には、これでJTIの「マイホーム借上制度」を使えば老後資金を確保できると安心しました。
その後、住宅金融支援機構が「リ・バース60」を制度化して、定住型リバースモーゲジを提供するようになり、住宅を資金化する選択肢が多くなりました。35年持ち続けた夢が叶いつつあります。
JTIが広く活用されることを期待しています。
法人概要
法人名 一般社団法人 移住・住みかえ支援機構
英文名 Japan Trans-housing Institute(JTI)
設立 2006年4月18日
本社 〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル 6階
基金 4,500万円
代表理事 大垣 尚司(青山学院大学教授・金融技術研究所所長)
理事 合田 純一(一般財団法人 住宅保証支援機構 理事長)
伊藤 明子(株式会社まち・ひと・しごと研究所 代表取締役)
監事 村本 孜(成城大学名誉教授)
主要業務
マイホーム借上げ制度の実施
JTIの「マイホーム借上げ制度」は、シニアの皆さま(50歳以上)のマイホームを借上げ、国の基金によるサポートも得て、安定した賃料収入を保証するものです。1人目の入居者が決定して以降は、制度利用者(オーナー)は入居者のいるいないにかかわらず、JTIを通じて賃料収入を得ることができます。
かせるストックの実施
JTIが定める耐久性、長期にわたるメンテナンス制度を備えた新築住宅を、「かせるストック」(移住・住みかえ支援適合住宅)として認定します。認定を受けた住宅は、「マイホーム借上げ制度」の通常の利用条件である50歳を待たずに、簡単な手続きでいつでも借上げ制度を利用することができます。JTIではこの制度を通じて、日本に社会の財産として役立つ、長寿命住宅が増えることを願っています。
残価設定型住宅ローンの実施
長期住宅ローンと金利上昇リスクに備え、あらかじめJTIが設定する残価設定月以降に行使することができる2つのオプション(借主が行使できる権利)を付加したものです。役職定年や退職などの収入減で住宅ローンの返済に不安となった際、「返済額軽減オプション」により残価設定月以降の返済額を大幅に軽減することができますので、住宅の買いやすさ「アフォーダビリティ」に貢献していきます。
転貸を通じた子育て支援と良質な住宅ストックの循環
皆さまから借上げたマイホームは耐震性能を確認の上、子育て中の若年層を中心に転貸して運用します。ゆとりある住環境の提供を通じて、JTIは子育て世代を支援するとともに、良質な住宅ストックの循環を図ります。
住宅の資産化に向けた制度の開発
近年、問題になっている空き家の流通促進を図り、賃貸住宅として再生・資産化すべく制度の開発を進めています。
新しい金融商品の開発・提供
金融機関と提携して、様々な金融商品(ローン)を利用者に提供してまいります。
住みかえ支援に関する情報提供
中立機関として、さまざまな移住・住み替え支援を実施している地方公共団体や民間企業から情報を収集し、サイトなどを通して情報提供をします。
資格制度ハウジングライフ(住生活)プランナーの運営
資格制度である「ハウジングライフ(住生活)プランナー」の運営・管理を行なっています。
協賛社員等
(五十音順)
旭化成ホームズ株式会社
朝日リビング株式会社
株式会社ASSETIA
SBIアルヒ株式会社
株式会社家守り
一般社団法人 石川県木造住宅協会
株式会社エス・エム・エス
株式会社エヌ・シー・エヌ
京王電鉄株式会社
京阪電鉄不動産株式会社
一般社団法人JBN・全国工務店協会
SHOWA GROUP株式会社
株式会社スペース
住友林業株式会社
積水化学工業株式会社
一般社団法人全国賃貸不動産管理業協会
第一生命保険株式会社
大和ハウス工業株式会社
東武鉄道株式会社
トヨタホーム株式会社
日本住宅ローン株式会社
日本木造住宅耐震補強事業者協同組合
株式会社ハウス・デポ・パートナーズ
パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社
パナソニック ホームズ株式会社
フリージアハウス株式会社
株式会社北洲
ポラテック株式会社
ミサワホーム株式会社
株式会社ヤマダホームズ
株式会社ロゴスホールディングス
地域のJTI協賛事業者/ 協働している自治体一覧
JTIでは地方公共団体と連携し、役所に相談窓口を設置するなど、住み替えの促進や空き家の活用に取り組んでいます。
協賛事業者とは
JTIと協賛事業者契約を結んでいる全国各地の事業者です。JTI認定の資格である「ハウジングライフ(住生活)プランナー」を所有している人間が所属しており「マイホーム借上げ制度」のご利用をサポートします。
※現在協賛事業者がいない地域につきましても、大手協賛社員のネットワークや業界団体のご協力を通じてカバーいたします。お気軽にJTIまでお問い合わせください。
協働している自治体とは
JTIでは地方公共団体と連携し、役所に相談窓口を設置するなど、住み替えの促進や空き家の活用に取り組んでいます。